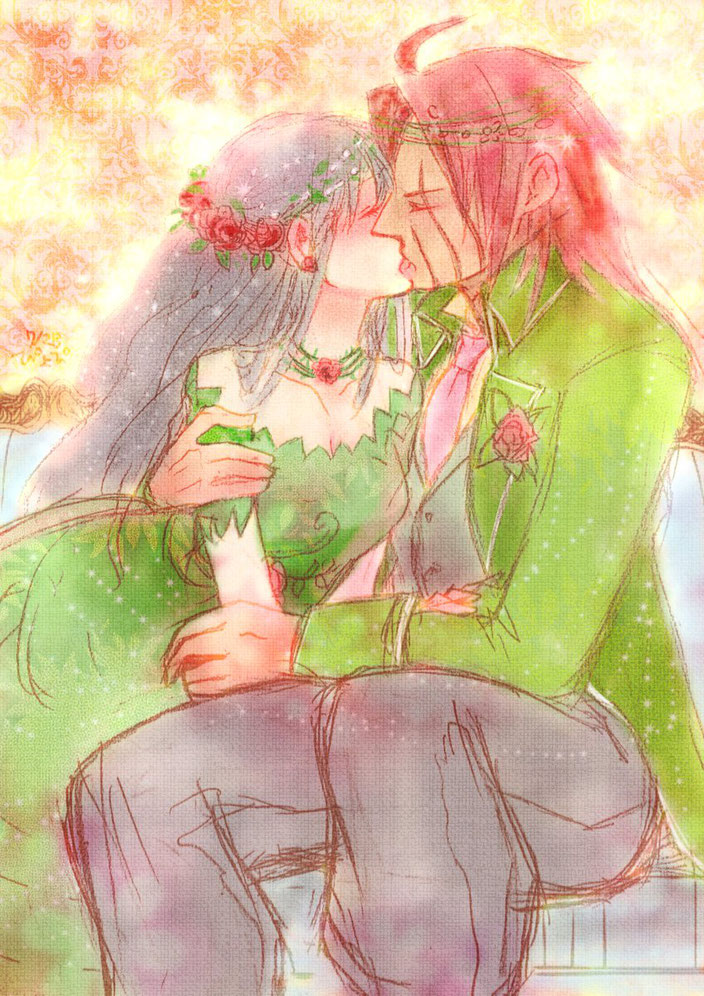「それでは新郎新婦は前へ…。」
神官の言葉と共に、エドワルドさんと共にならんで神殿の紅いカーペットの上を歩く。
両脇並ぶ椅子には、親しい人達の顔が並びみな祝福の笑みを浮かべている。
通路の一番前まで来ると、神官の挨拶と共に、式が始められた。
数か月前―――。
エドワルドさんが負傷して片目の視力を失ってから、私は毎日を彼の家で過ごしていた。
保守的なこの国では、結婚もしていないのに節操がないと言われる事もあったが、
そんな事彼と共に居られる事に比べたら、何て言う事はなかった。
厳格な父も、彼の助けになるなら構わないと、許してくれた。
私はどれだけの人に護られているのだろうと、この所良く思う。
母のいない私を父が守り育み、隊に入ってからは仲間に守られている。
そしてエドワルドさんにも。
自分が誰かのを護った事があるだろうか?いつも与えて貰うばかりだ。
視力を失ってもなお彼は私を護る為に尽力している。
私は…彼の為に何が出来るだろう。
いつまでも護られるだけの自分が不甲斐ない。
隣で日課になった筋トレをする彼を観ながら思わず訊ねた。
「あの…エドワルドさん。」
「んー…?」
体を動かす事は辞めず気の抜けた返事をする彼に
「私といるの…負担じゃない?」
「は…?何言ってんだ?」
ドサッとトレーニング用の砂袋を落とすと、汗だくの顔をこちらに向ける。
顔にはくっきりと爪で抉られた痕が残っている。
それを見るとチクリと心がまだ痛む。
誰のせいでもない。自分たちが互いに未熟だった事だ。そう仲間からは言われた。
自分でもそう思う。それでもあの時…とずっと心に積み石が乗せられている感じがする。
彼は近寄り手渡したタオルで汗を拭きながら、
「負担って、なんの?」と短く言った。
「んー…何だろう。私、ずっと護られてばっかりだから。エドワルドさんは傷ついても、
尚貴方は私をまもろうとしてくれてる。私も訓練は頑張ってしてるつもりだけど…。
私はエドワルドさんの助けになってるのかなって。」
「え、何でそんな事言い出したんだ?」
「別に理由は…。」
「んー。難しい事わかんねぇけど、俺はラクシュミがいてくれればそれでいいよ?」
「どうして?」
「んー…?わかんね。」
クシャっと八重歯を出して笑う彼とは対照的に自分の顔は曇る。
彼のその天真爛漫な明るさが好きだ。人には単純すぎると言われるけれど、
それでも彼のそんな明るさと優しさが大好きだ。
彼は私のどこが良いんだろう?長く一緒に居るけれど、唐突に自信も気持ちも分らなくなってしまった。
「あ…俺なんか、変な事言ったか?」と焦り気味に言う彼に、フルフルと首をふる。
「うぅん…でも…。ごめん…。暫く家に戻ってもいいかな…。」
「ぅえっ??何で…??」
オロオロするエドワルドさんを背に、私は彼の家を飛び出していた。
「はぁ~…バカだなぁ…。家、飛び出す事もなかった…よね…。」
トボトボと街を歩き、どこをどう歩いて来たか分からないけど、気が付くと二ヴの丘へと来ていた。
もう夕日が沈みかけているその場所に人気はなく、サワサワと夏草が揺れ、そこは相変わらず穏やかで心地よい。
胸一杯に空気を吸い込んで深く息を吐きだすと、胸の中に溜まる淀んだものまでも洗われる気がした。
「お家…帰れないしな…。」
草原に膝を抱えて座り目を瞑り、彼との出会いからずっとここに至るまでを思い返していた。
入隊した時に一緒にお酒を飲んで騒いだこと。
共に探索に出かけては、帰りにご飯を食べてそれがとても楽しくて、食事がこれまでになく美味しく感じた事。
初めてお酒を飲んで酔いつぶれて、お家まで運んでもらった事。
細かな思いではいっぱいある。
そして、彼が私を護り傷ついてしまった事…。
ちゃんと二人で話して納得したはずなのに、彼の毎日の生活の不便さを目の当たりにすると、
心に黒い水滴がぽたぽたと落ちて影を作って行く。
一緒に居る事が当たり前の様に思っていたけれど、今の私達に縛る鎖は何もない。
一時、「婚約」をしたけれど騒動でそのまま話は流れてしまった切りになっている。
だから私達には…何もない。
「どうしたいのかしら…私。」
ずっと一緒に居られたら。そう思う気持ちは本当だ。
けれど、それは護られるだけの自分では居たくない。彼を護れる自分になりたい。
並んで共に歩く事が出来れば、の話だ。
でも、その”護り方”が分からない。
どれだけ頑張っても能力的に彼を上回る事は出来ないし、お家の事だって立派に出来る訳でもない。
「ママ…どうしたらいいのかな…。」
空を見上げて亡き母の面影を追いながら小さく呟いた。
”ぃっくしっ!”
何だかその場にはない音に気が付きうっすらと目を開けると、もう日はとっぷりと暮れ、空は月と星の世界に代わっていた。
肩には近衛の腰巻が掛けてある。
どうやら知らない間に岩にもたれて眠ってしまった様だった。
その布を抱きしめ、横を向くとそこにはエドワルドさんが座って鼻を擦っていた。
「え…どうしたの?」
「どうしたのって…プッ!」
一しきり腹を抱えて笑う様子に、恥ずかしくなり顔が赤く熱を持つのを感じた。
「はぁ~ぁっ…おっかし…。」
「そ、そんなに変な事言ったかな…。」
「うん、言った。」
「そんな事ないよ…。」
「だってさ、急に飛び出してって、蝶飛ばしてもウロウロしてちっとも見つかんねぇし、居たと思ったら寝てんぜ?挙句『どうしたの?』って…こっちの台詞だって!」
というと、また思い出したように笑う。
「そ、そっか…。ご、ごめん。」
「いや、いいよ。そんな事。ラクシュミらしいなぁって思っただけだから。」
「私らしい…?」
「そ。ラクシュミらしい。間が抜けてて、一生懸命で、真面目すぎて、変に考え込む。」
「…それ、バカって言いたい?」
「んー。まぁそうだな。」
「酷い…。」
「いや、ごめん。でもちょっと違う。」
と言うと不意に腕を引っ張り自分の懐へと抱き寄せると、
「自分の事は後回しで全部誰かの為にそうする所。バカだなーって思う。でも俺はそんなとこが好きだ。」
「へ…?」
「俺さラクシュミに言われてちょっと考えて見たんだ。『負担になってないか』って何で急に言い始めたのかなってさ。」
「うん…。」
「あー。俺バカだから難しい事上手く言えないけど、先ずそれの返事から言えば、負担何て思ってないから。」
と抱き締める腕を強めると続けて話始める。
「それから、どうしてそう言い始めたのかなって考えて…。
ラクシュミずっと俺が怪我してから俺の事ばっかだっただろ?俺も自分の事で精一杯でラクシュミをちゃんと見てなかった。
ごめんなぁ。側に居る事が当たり前で一緒に居る事が空気みたいで、大事なのに大事にしてなかった。」
「そんな事…!」
と遮る様に口を挟もとすると、
「まぁ最後まで聞けよ。俺が怪我したのは俺が悪い。けどラクシュミも悪い。近衛だからな?それは話しただろ?」
「うん…。でも…。」
「そう、『でも』なんだよ。」
「え…?」
「俺のこの傷見る度にラクシュミは傷ついてた。自分がもっと強かったら―って思ってただろ?」
「…。」
「なのに、俺が不自由になって自分の気持ちは放り出して、俺の眼になって手になって足になって?助ける事ばっかりだった。
俺もそれが常になっちまって甘えてたんだなぁ…って。やっと気づいたよ。」
「それは、私がしたいから…した事でしょ…。」
「まぁそうだけどさ、でも俺を気遣ってばっかりいる間、ラクシュミは?俺に甘えてこなかっただろ?」
そう言われて、少し考える。
思えばずっと自分の気持ちはどこかに置いて来た気もする。それどころではなかったから。
「…うん。気が付かなかったな。」
「ごめんな…。俺さ、さっきいい加減な事言ったけど、あれが全部本音何だよな。」
「うん??」
「”ラクシュミが一緒に居てくれるだけでいい”それが全部。」
「え…どういう事?」
「んー…ラクシュミが俺と一緒に居て、一緒に笑って、一緒に並んで歩いてくれたら、それだけで俺は十分すぎるほど幸せっていうか…さ。
物理的なもんは俺のが強ぇかもしれないけど、精神的強さだったり俺の良心でいてくれたりは、ラクシュミが持ってる。俺はそれに助けられてる。そう思うよ。」
「私が…助ける…?」
思いもしない言葉に驚き彼の顔を見る。
と、いつものようにニシシと笑いながら頬を赤らめる彼の顔が見えた。
「でさ…。」
笑みを少し残しながらも真面目な顔になると。
「ちょっと目、閉じててくれるか?」と言った。
「う、ん…。」
何だろうと言われたまま目を閉じると、不意に指に冷たい感触が走る。
「ひゃっ!?な、何??」と目を開けそのひんやりした場所をみると、
少し大きめな真新しいリングが左の薬指にはめられていた。
「あれ…ご、ごめん、サイズちょっとデカかったな。急いでここに来る前に買ってきたからさ。」
「こ、これって…。」
そう言って彼の手をみるとお揃いのデザインをしたリングが同じ指にはまっていた。
「へへ…。あー…。色々あって、さ。随分待たせちまったけど、今度こそ…結婚しよ。ダメか…?」
不意の事で本当なら手放しで喜ぶべき所なのに、返事にまごついて答えずにいたら、
「今日、ラクシュミが家出てって、1人になって、思ったんだ。あれ…この家って、こんな広かったっけってさ。
勝手だけど、そこにいるはずのお前が居なくて、何だかスゲェ焦った。そんだけもう俺ん中に浸透してんだなって。そう思ったら家飛び出てた。」
そう言いながら苦笑する彼の顔はとても照れくさそうで。それでいてとても晴れやかな顔をしていた。
その顔を見て笑みがこぼれた。
「プッ…もう…。そんな自信満々に、私が絶対OKするみたいな顔で言う何て、ズルい。」
笑ながら、そういえばこんな風に心から笑ったのって、何時ぶりだろう?と思っていた。
「えー。ダメかぁ~?」
口でそんな事を言いながらも、全くぶれる様子がない彼が可笑しくて。
「プッ…くっ…っはは!うん…結婚…して下さい。」
そう言って笑った。
「やった!もう今度は絶対何も起きないようにするからな!」
「ちょっと、そんな事分らないじゃない。」
「まぁ、そうだな。けど起きないようにする!」
「ふふ…でもまぁ~…とりあえずこのリングは、直してもらわなきゃね。」
「う…ホントごめん。」
と徐に立ち上ると私の手を引き立たせ、
「幸せに…なろうな。二人で。」
「うん…二人で。」
と力いっぱい抱き締められ口づけを交わした。
―――現在。
「それでは、ここにこの二人を夫婦と認め、結婚の儀を終わります。ご臨席の皆様は新郎新婦に盛大な拍手でお見送り下さい。」
神父の言葉に背中を押され、神殿の通路を出口へと進む。
来賓からは賛辞の言葉が飛び、その中には父クロードや、義理の兄となったエリック隊長たちの姿があった。
手を繋ぐ私達の指には、ちゃんとサイズピッタリに合わせて貰ったリングが光っていた。
神殿の出口を出て、これから祝いの席が開かれる前に、一度新居へ行こうとしていたその時、
老齢の巫女殿に私は声をかけられた。
「ちょっと新郎殿、待ってて貰えるかい。女同士で話しておかなきゃいけない事が有るからね。なぁに、直ぐ済むからね。」
「え?あ、はい…。」
通常だったらそんな事はなく、私も驚いた。
その場にエドワルドさんを残し、女史の後へと突いて巫女の部屋へとついて行くと。
「まぁ、ちょっとそこに座っとくれ。」
「あ、はい…。」
言われるまま座ると、唐突にその女史はこういった。
「あんた。多分だけどねぇ、妊娠してる。その為にちょっと来て貰ったよ。身に、覚えはあるかい?」
「え…??に、妊娠??」
「あぁそうだよ。で?覚えはあんのかい。」
「そ、それは…その…はぃ…。」
「まぁったく。仕方ない子だねぇ。どれちょっと検査するよ?すぐ済むから腕出しな。」
おずおずと腕を差し出すと採血をされ、判定を待つ。
「あぁやっぱり。ビンゴだよ。まぁねぇ、中調べて見なきゃ、絶対とは言えないけども、十中八九間違いない。相手は、今の旦那で間違いないかい?」
「は、はい…。」
「そうか、そりゃ良かったよ。それじゃぁ旦那に話してやんな。それから…。」
女史が色々と言ってた気がしたが、後半の方はもう頭の中が真っ白で何が何だか分からなかった。
”妊娠…?赤ちゃんが…いるの???”
どうしようと思いながら、巫女の部屋を出ると、待っていたエドワルド君の元へと近寄る。
青ざめてる私の顔を見て、
「ど、どうした??具合でも悪いのか??」と心配そうに顔を覗き込んでくる。
「エド…ワル、ド…さん…。」
倒れそうになり彼に抱えられながら神殿近くの花壇の縁へと腰かけた。
「どうした?一体何があったんだ??」
「…かちゃん…。」
「え…?何??」
「ぁ…かちゃ…」
「ん????」
「あ、かちゃ…ん…出来てるって…。」
「え??あ、かちゃん?あ、ええ??赤ちゃん!?え、俺達の!?えぇええ~???」
「ご、ごめんね。何か…ごめん。」
「えっ!え??何で謝るの!?スゲーじゃん!!俺たちの子だぞ?しかも今日分かったって、すごくねー?」
「い、いいの…?だって、そんな…。」
「良いに決まってんだろ!?うわーーー。どうする?俺パパだってよ。スゲェ!!」
そう言うと私を高く抱き上げる。
「有難うラクシュミ!あ!そっか、こんなんしたらダメだよな。ごめん。」
とそっと大切に地面へとおろし、再び花壇の縁へと座らせると、嬉しそうに笑う。
その心から幸せそうに笑う顔に、私もやっと嬉しくなり彼をそっと抱きしめた。
「有難う。エドワルドさん…。幸せに。なろうね。」
「あぁ…ちょっと予定外に早くなったけど、3人で。幸せになろう。」
そう言って優しく深く彼と口づけを交わした。
困難はきっとこの先も色々とあるだろう。
けれど、彼と2人なら必ず道を見つけて進んでいける。そう心に深く誓った。
永久を共に…。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から